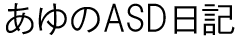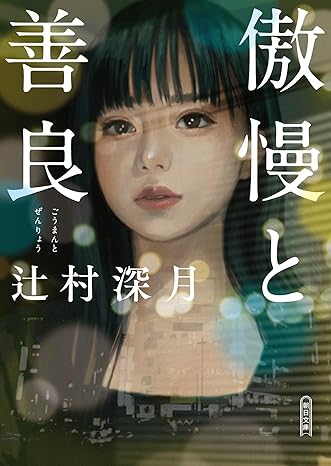「過去の傲慢と偏見、現代の傲慢と善良さ――結婚事情の変遷」
過去の時代、恋愛や結婚においては、身分の高低が大きな障壁となっていました。しかし、現代の日本では、目に見える身分差別は薄れてきました。それでもなお、恋愛や結婚がうまくいかない理由は、「傲慢と善良さ」にあるようです。
皆が自らの価値観に固執し、同時に善良を装いながらも、他者の期待に縛られることが多く、その結果、自己を見失うことがあります。この不思議な時代において、過去の傲慢と偏見と現代の結婚事情との関連性を考えると、興味深い発見があるかもしれません。
特に刺さった部分は下記です。
「今日、小野里さんとお話ししていて何度も出た言葉ですけど、僕も実際、婚活していて、その感覚に苦しめられた気がするんです。相手と会って、条件は申し分ないはずなのに、ピンとこないから決断できない。――結婚した友人たちからは、ピンとなんてくるはずない、と言われたりもしましたけど」
ピンとこない、は魔の言葉だ。それさえあれば決断できるのに、その感覚がないから、どれだけ人に説得されようと、自分で自分に言い聞かそうと、その相手に決められない。
真実もここで、その感覚に苦しめられたのではないか。架のように。
「――ピンとこない、の正体について、私なりのお答えはありますよ」
ふいに小野里が言って、架は目を見開いた。
「何ですか」
あの感覚に正体などあるのか。架の視線を、小野里が正面から受け止める。着物の帯の下辺りに上品に手を添えた老婦人がまた笑う。
「ピンとこない、の正体は、その人が、自分につけている値段です」
吸いこんだ息を、そのまま止めた。小野里を見る。彼女が続けた。
「値段、という言い方が悪ければ、点数と言い換えてもいいかもしれません。その人が無意識に自分はいくら、何点とつけた点数に見合う相手が来なければ、人は、“ピンとこない”と言います。――私の価値はこんなに低くない。もっと高い相手でなければ、私の値段とは釣り合わない」
架は言葉もなく小野里を見ていた。
「ささやかな幸せを望むだけ、と言いながら、皆さん、ご自分につけていらっしゃる値段は相当お高いですよ。ピンとくる、こないの感覚は、相手を鏡のようにして見る、皆さんご自身の自己評価額なんです」
ー>この文章から浮かび上がるのは、自己評価と相手への期待が絡み合い、結婚相手を選ぶ際に大きな影響を与えることです。自分の「値段」や「点数」を意識せずにはいられない時代において、相手が自らの期待に見合うかどうかが、判断基準となっています。この考え方は、自己評価が高いほど相手への要求も高まり、結果的に相手に対する採用基準が厳しくなるという矛盾を内包しています。
自己評価の高さと相手への期待の高さが一致しない限り、「ピンとこない」と感じることがあります。この言葉が指し示すのは、現代人が抱える自己評価の問題だけでなく、恋愛や結婚における人間関係の複雑さや繊細さを考えさせられるところです。
婚活がうまくいく人とうまくいかない人の差は何か。尋ねた架に彼女が答えたのだ。
――うまくいくのは、自分が欲しいものがちゃんとわかっている人です。自分の生活を今後どうしていきたいかが見えている人。ビジョンのある人。
ー>自己認識と目標設定が明確であることは、婚活において成功するための鍵となります。自らを理解し、求めるものを明確にすることで、理想のパートナーとのマッチングもスムーズになります。このような内省と自己啓発を通じて、より満足のいく関係を築くための土台が整います。
ジャネットに以前、「あなたの行動力と語学力が羨ましい」と直接言ったことがあるけれど、その時、ジャネットが「真実は、自分の言葉で外国人とちゃんと話したいと思う?どこか違う国で暮らしたいと思うの?」と聞いてきた。
「あなたがそうしたい、と強く思わないのだったら、人生はあなたの好きなことだけでいいの。興味が持てないことは恥ではないから」
その言葉に、どれだけ救われたか。何かに興味が持てないことを、ずっと、いろんな人たちからバカにされてきたように思ったけど、それは、バカにするその人たちの方に問題があるのだ、と思えた。
ー>興味が持てないことに対して自責の念を感じる必要はなく、それは他人の期待に応えることよりも、自分自身の幸福を追求することが重要であることを示唆しています。この言葉が真実に、そして私にもたらした解放感は、自己受容の大切さを再確認させるものであり、他者の意見に左右されずに自分らしく生きる勇気を与えてくれました。
この人に、私はかつて百点をつけていた。
物慣れて、今日だって見も知らぬ誰か他人相手に手土産が持参できるくらいに気を遣えて、見た目もスマートで。そんなところが、私は気に入っていたのだと思っていた。
婚活で女性に気を遣える男性なんてそう残っていませんよ――とアドバイスされて、こんな条件のいい人ならば、と頑張った。架の女友達の言う通りだ。こんな条件のいい人が、残っていると思わなかった。
けれど、違う。
もっと、素直に認めてよかった。
この人は――とても鈍感なのだ。
私の嘘を許してしまえるくらいに。
ー>この部分、私も共感します。私も鈍感な人の方が好みです。鈍感であることは、柔軟で優しいと感じます。私はASD(アスペルガー症候群)なので、過度に敏感な人と付き合うと、私自身が疲れてしまうことがあります。だからこそ、真実の言う鈍感な人という表現に共感しました。
下記は朝井リョウさんの解説文です。
善良でいい子、言い換えれば自分の意思で何も選んでこなかったこれまでの歴史が、いざ何かを“選ぶ”場面となったとき、真実を傲慢にしてしまうのだ。
この側面の炙り出し方が非常に鮮やかで、かつ、深く身に沁みた。謙虚と自己愛の強さは両立するのだという鋭い発見は、現代をうっすらと覆う病理のようなものを見事に言い当てていると感じた。
ー>自己を大切にすることと他者への配慮のバランスを取ることは、容易ではありませんが、現代の日本人に多く見られる一種の病理のようなものだと認識し、多くの人に共通する重要なテーマであることを改めて感じました。